
あかたのだいぶつ
由利本荘市赤田上田表
最終更新:2025/05/30


-

- 開山:安永4年(1775)
- 開祖:是山和尚
- 宗派:曹洞宗
- 例祭日:8月22日
- 神事:赤田大仏祭
- 秋田三十三観音霊場 第8番札所
-
- 御詠歌:荒沢座の 神と仏と人問はば 誠に響く 松風の音
-

- 像高:7,787m
- 材質:杉材の寄木造りで金箔押し
- 建立:寛政6年(1792)※明治21年に焼失
- 再建:明治25年(1892)
- 仏師:一柳齋 家慶 他5名
「十一面観世音菩薩立像」
[昭和六十一年二月十三日指定]
国登録有形文化財「長谷寺大仏殿」
[平成二十五年十二月二十四日登録]

長谷寺(本荘地域赤田地区)は、是山泰覚が安永四(一七七五)年に開山し、亀田藩主岩城氏の祈願所とされた寺院です。
「赤田の大仏」として親しまれている長谷寺式の十一面観世音菩薩立像は、是山泰覚が天明四(一七八四)年に奈良と鎌倉の長谷寺にあやかって造立を発願し、三年の歳月を要して天明六(一七八六)年に完成させたものです。
大仏殿は寛政四(一七九二)年から建築に着手し、寛政六(一七九四)年に完成しましたが、 明治二十一(一八八八)年客殿からの失火により、堂塔伽藍が全焼しました。
現在の大仏は、当時本荘町大町の呉服商であった佐々木藤吉の寄進により土川村(現大仙市土川)の仏師・一柳齋家慶(松田善造)外五名が制作したもので、明治二十五(一八九二)年に復元され、明治二十九(一八九六)年に大仏開眼落慶法要が行われました。
像高は二丈六尺〔七.八七八m〕、杉材の寄木造りで金箔が押されています。
明治二十六(一八九三)年に再建された大仏殿は、当初の建築様式や規模を忠実に復元した、総高七丈と言われる約二十一.二の上下二層の建造物です。
上下層の四面に擬宝珠高欄が巡り、上層南面の正面側には奈良東大寺大仏殿と同様の観相窓があります。
外側には切目録が廻り、一八本の八角の側柱が建物を支えています。
屋根は、再建当初木端葺きでしたが、昭和二十年代に銅板に葺き替えています。
また、内部は大仏を安置するため吹き抜けになっており、大仏周囲の円柱の入側柱4本が、下層から上層へ一本通しで大仏殿全体を支えています。
大仏殿は彫刻や絵画などの装飾も豊富であり、棟梁を務めた南内越村(現本荘地域川口)の宮大工・小川松四郎による彫刻をはじめ、大仏上部格天井には本荘藩御用絵師の増田象江(きさえ)による「三十六禽之図」、板扉絵には明治時代の名工と称された北内越村(現大内地域中館)の松雲洞羽嶽(堀藤兵衛)による「三十六歌仙」が描かれています。
さらに、下層の寺号額、上層の山号額は、寛政七(一七九五)年に亀田藩主岩城隆怒(たかのり)により山号寺号を受けた際の揮毫を、再建時に復元したものです。
長谷寺大仏殿は、秋田県唯一の大規模な仏殿であり、秋田県の近代寺院の構造、装飾等の様式を知るうえで重要な建造物です。また、毎年八月二十一・二十二日に行われる「赤田大仏祭り」は、平成九(一九九七)年に秋田県の無形文化財に指定されており、大仏殿をめぐる多くの文化財が継承されていることからも貴重であるといえます。
長谷寺 由利本荘市教育委員会
『赤田の大仏』として親しまれている長谷寺式の十一面観世音菩薩立像は、是山泰覚が奈良と鎌倉の長谷寺にあやかって造立を発願し、3年の歳月を要して完成させた。
拝観は自由で、像に近づくとセンサーが感知してライトアップされる。
巨大モノ好きの自分としては外観の大仏殿だけでも血沸き肉躍る。
他に県内の巨大建造物といえば田沢湖町の金色大観音が挙げられるがこちらも劣らず名刹である。
実は有事の際に起動・発進する仏型決戦兵k…みたいな冗談を書くと怒られそうなので程々にしておく。

- 棟梁を務めた南内越村(現川口地区)の宮大工・小川松四郎による彫刻
- 大仏上部格天井には本荘藩御用絵師の増田象江(きさえ)による「三十六禽之図」
- 板扉絵には明治時代の名工と称された北内越村(現大内地域中館)の松雲洞羽嶽(堀藤兵衛)による「三十六歌仙」
長谷寺大仏殿は、秋田県唯一の大規模な仏殿であり、上下層の四面に擬宝珠高欄が巡り、上層南面の正面側には奈良東大寺大仏殿と同様の観相窓があり、内部は大仏を安置するため吹き抜けになっている。
彫刻や絵画などの装飾も豊富に配置されている。

- 祭日:8月下旬(22日~24日)
- 内容:平岡獅子踊、赤田獅子舞、シャギリ 他
- 奉納寺社:長谷寺、赤田神明社

「赤田大仏祭り」は、毎年八月二十二日を中心にして行われる華やかで とても賑やかな祭礼です。
二十二日の午後一時三十分頃、鳥前寺地区にある神明社に前日から安置されている長谷寺の赤田大仏の胎内仏を神輿に乗せて、約一キロメートルの田園の中の道のりをクネリ(渡御行列)をつくり、長谷寺で向かって出発します。
クネリは、色彩豊かな幡や御輿に、是山禅師が教えたとされる獅子舞、獅子踊り、シャギリなど数多くの服やかな民俗芸能が加わり、それぞれ大仏殿を三周して奉納します。
この祭礼は、安永九年(一七八〇)に、丈六阿弥陀如来像の遷座にあたって行われたのが 始まりとされ、観世音菩薩が豊作を予祝してくれる農耕信仰と長谷寺開基の是山禅師への 崇敬心を伴って、赤田町内が長い間継承し続けている祭礼です。
明治の神仏分離以降も長谷寺と神明社が一体となった神仏習合の形態を色濃く残す貴重な祭礼として、平成九年に秋田県無形民俗文化財の指定を受けています。
秋田、赤田の大仏祭り 神仏習合は他にも各地に。でも、秋田は多い。が、昔は神も仏も同じと。奇跡の習合 残さなければ… pic.twitter.com/OPbPEcc2j1
— 片野年詞 (@tositugu_katano) August 25, 2019
安永9年(1780)に、丈六阿弥陀如来像の遷座にあたって行われたのが始まりとされ、観世音菩薩が豊作を予祝してくれる農耕信仰と長谷寺開基の是山禅師への崇敬心からなる。
明治の神仏分離以降も長谷寺と神明社が一体となった神仏習合の形態を色濃く残す貴重な祭礼として知られる。
22日の午後1時30分頃、鳥前寺地区にある神明社に前日から安置されている長谷寺の赤田大仏の胎内仏を神輿に乗せ、田園の中の道のりをクネリ(渡御行列、獅子舞・シャギリ)をつくり、長谷寺で向かって出発し、それぞれ大仏殿を3周して奉納する。
| 駐車場 | 案内板 | トイレ |
| 〇 | 〇 | 〇 |
伝統文化等保存伝習施設・東光館
由利本荘市赤田上田表95

- 営業時間:8:30~17:15
- 料金:
赤田大仏、長谷寺に関する資料展示、ブルーベリー園
- 神仏習合
- 秋田六郡三十三観音霊場
◆参考文献
- 各種説明板
取材日:2018/05/20
2024/11/29































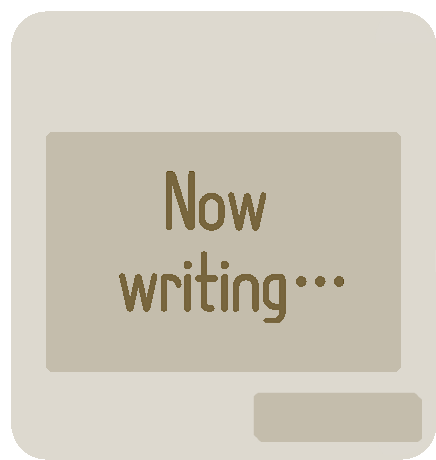



コメントをお書きください
降魔成道 (木曜日, 11 10月 2018 20:59)
私は昨年5月に秋田三十三観音霊場巡礼で参拝しました。迫力ありますよね。赤田大仏祭りは私も行ってみたいです。
菅井マスミ (金曜日, 12 10月 2018 19:24)
>降魔成道さま
コメントありがとうございます!
霊場巡礼、私もやってみたいですね。御朱印帳は用意してるのですが…。
大仏祭り見ることができたらまたレポしたいと思います。