
はちりゅうのやしろ
男鹿市舩越
最終更新:2024/12/28

- 来訪:文化元年(1804)8月
- 年齢:51歳
- 書名:男鹿の秋風
- 形式:日記、図絵
◆八龍神社 由緒
- 山域:
- 標高:
- 祭祀:
- 宿泊:
- 別名:
あ

文化元年(一八〇四)八月二十一日、八龍の社に詣でる 《男鹿の秋風》
八郎という者が難蔵法師との争いに負け大蛇となってこの湖水に入ったという伝説を残す
平成二十三年九月 男鹿市教育委員会
参道鳥居にジオパーク説明板とともに建立。
八郎潟漁業者の信仰があつい八龍神社は、かつて八郎潟に突き出た砂州になっていた。
干拓前の八郎潟では漁業が盛んで、漁業者が八龍神に豊漁を感謝し、魚の霊を鎮めるために石碑を建てました。
最も古い「湖鰡供養塚」は文久元年(1861)に建てられています。
また船越の漁業者や政治家が八龍神への感謝として、護岸用の石を奉納して石碑を建てています。
これらの石碑は、八龍神に対する信仰心を表す貴重な民俗資料として市の指定文化財になっています。
(説明板より)

(平成17年3月14日)
八郎潟漁業者の信仰があつい八龍神社は、かつて八郎潟に突き出た砂州になっていました。干拓前の八郎潟では漁業が盛んで、漁業者が八龍神に豊漁を感謝し、魚の霊を鎮めるために石碑を建てました。
最も古い「湖鰡供養塚」は文久元(1861)年に建てられています。また船越の漁業者や政治家が八龍神への感謝として、護岸用の石を奉納して石碑を建てています。
これらの石碑は、八龍神に対する信仰心を表す貴重な民俗資料として市の指定文化財になっています。また船越の漁業者や政治家が八龍神への感謝として、護岸用の石を奉納して石碑を建てています。
・魚類供養塚(建立年月日/高さ/幅(単位:cm))
①湖 鰡 供 養 塚…文久元(1861)年/100/55
②若鷺(鷲)供養塚…大正元(1912)年/100/77
③魚 類 供 養 塚…大正5(1916)年/113/76
④小 魚 供 養 塚…昭和9(1934)年/83/60
⑤鰡 供 養 塚…昭和16(1941)年/76/32 ・八龍神信仰碑(建立年月日/高さ/幅(単位:cm))
⑥湖岸石献納碑…大正4(1915)年/100/69
⑦竜 神 報徳碑…明治28(1895)年/210/89
(建立年月日/高さ/幅(単位:cm))
①湖 鰡 供 養 塚…文久元年(1861)/100/55
②若鷺(鷲)供養塚…大正元年(1912)/100/77
③魚 類 供 養 塚…大正5年(1916)/113/76
④小 魚 供 養 塚…昭和9年(1934)/83/60
⑤鰡 供 養 塚…昭和16年(1941)/76/32

- 駐車場:なし
- 案内板:なし
- トイレ:なし
◆参考文献
- 菅江真澄遊覧記第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一 訳
- 国立国会図書館デジタルコレクション
- 真澄紀行/菅江真澄資料センター
- 各種説明板
取材日:2016/06/07
2021/03/05































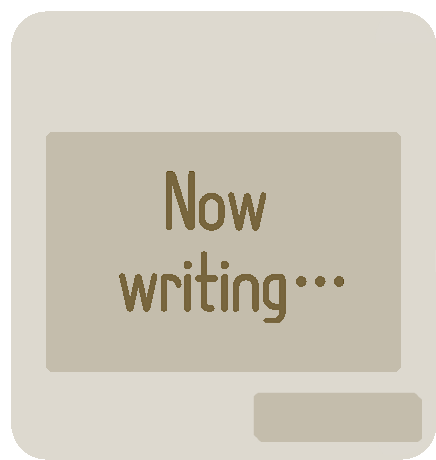


コメントをお書きください